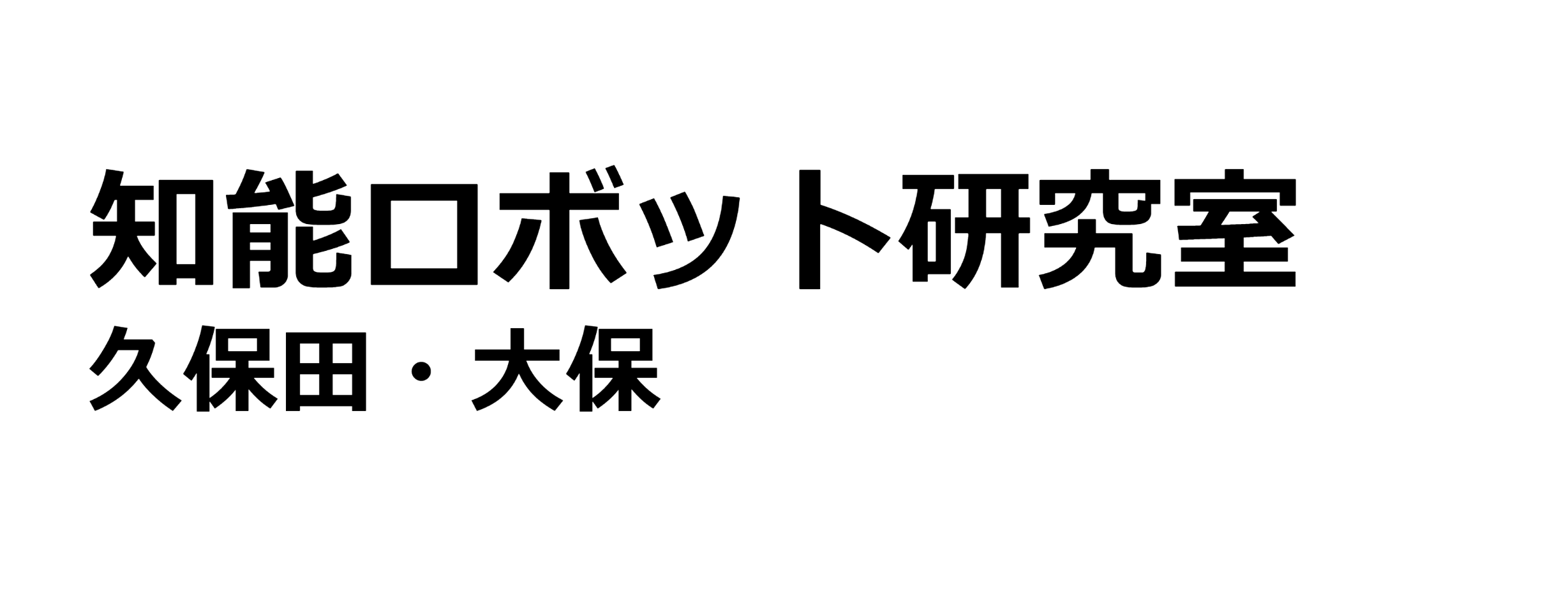知覚・認知・知能など「知」に関する原理を解明するために、ロボットを用いた構成論的な研究を進めています。応用研究では、情報技術・ネットワーク技術・ロボット技術を有機的に統合するための知能化技術に関する研究を通して、様々な社会的・工学的問題の解決に取り組んでいます。また、生態心理学や認知神経心理学などで得られた知見に基づき、人の能力を知り、人の尊厳を守り、人を支援するシステムを開発しています。具体的には、ロボットパートナーに関する研究開発のほか、高齢者や災害弱者への支援システムや認知運動療法システムに関する研究を行っています。
人にやさしいロボットパートナーを目指して
東京都立大学 システムデザイン研究科 知能ロボット研究室
人にやさしいロボットパートナーを目指して
東京都立大学 システムデザイン研究科 知能ロボット研究室
人にやさしいロボットパートナーを目指して
東京都立大学 システムデザイン研究科 知能ロボット研究室
次世代を切り開くロボットの知能化と実用化次世代を切り開くロボットの知能化と実用化
知覚・認知・知能など「知」に関する原理を解明するために、ロボットを用いた構成論的な研究を進めています。応用研究では、情報技術・ネットワーク技術・ロボット技術を有機的に統合するための知能化技術に関する研究を通して、様々な社会的・工学的問題の解決に取り組んでいます。また、生態心理学や認知神経心理学などで得られた知見に基づき、人の能力を知り、人の尊厳を守り、人を支援するシステムを開発しています。具体的には、ロボットパートナーに関する研究開発のほか、高齢者や災害弱者への支援システムや認知運動療法システムに関する研究を行っています。

研究室Blog:くぼらいふ
トレーラハウス型実験環境「リビングラボ」
トレーラハウス型実験環境「リビングラボ」


© 2021-2024 KUBOTA-LAB